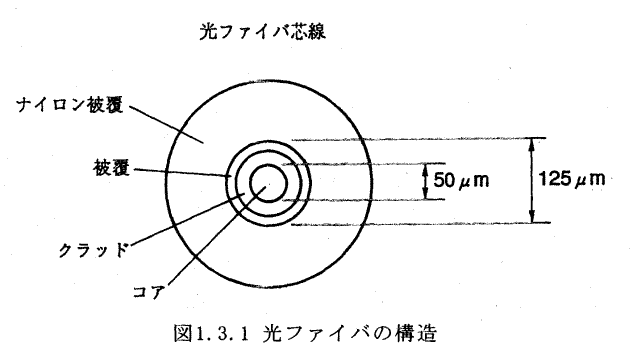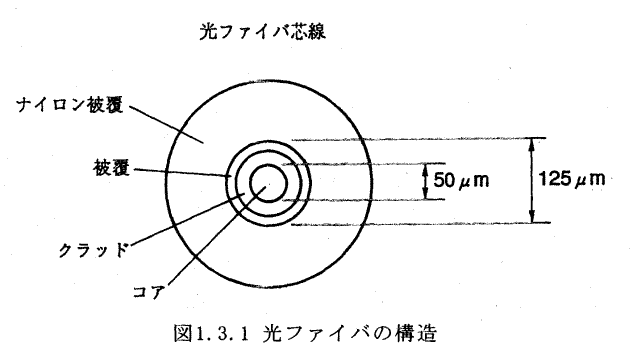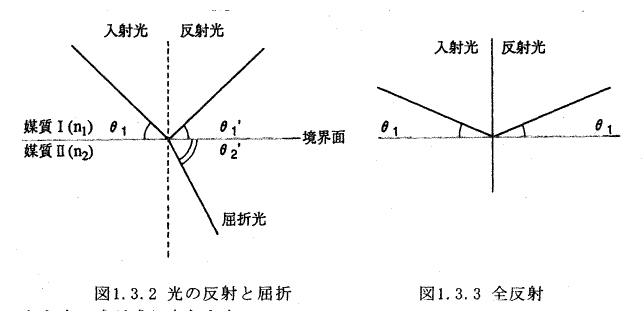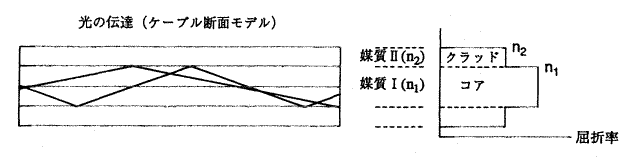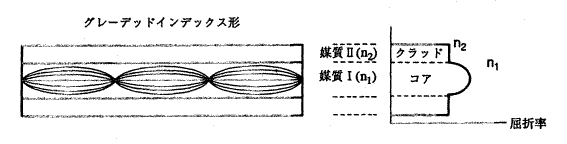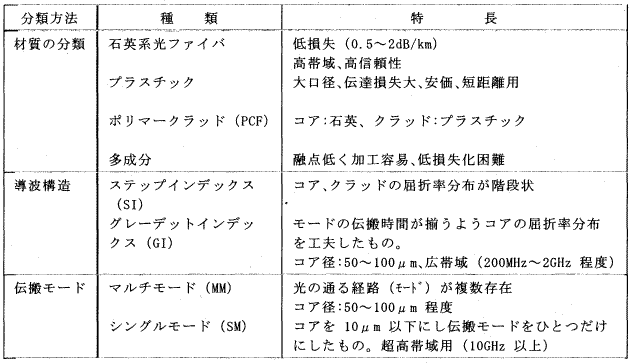1. 動作原理、解説
光通信の基礎
1. 光ファイバの光伝送原理
光ファイバは、光信号を伝える媒体で石英ガラス、プラスチックなどから作られた非常に細い繊維で屈折率の異なる2種類の材質を同心円にし、これに保護の被覆をした構造になっています。
中心の媒質をコアといい光信号の伝達する部分で、そのコアを囲んでいる媒質をクラッドといい、光を安定に閉じ込める役目をします。
それでは、光はどのようにしてコア内を伝達していくのでしょうか。光は、同じ媒質内では直進しますが、屈折率の異なる媒質の境界面では反射、屈折という現象が起きます。その屈折の度合いは、媒質によって異なります。水に入れたスプーンは曲がって見えますが、これは水と空気の屈折率が、異なるために起こる現象です。空気、水を屈折率nlの媒質Ⅰ、屈折率n2の媒質Ⅱにそれぞれ置きかえて、これを考えてみます。
入射角 θ1で入射される光は反射角θ1′= θ1で反射し、残りは媒質Ⅱへ透過し、その透過光は境界面に対しθ2で屈折します(図1.3.2参照)。
このとき次の式が成り立ちます。
COSθ1/COSθ2= n2/ n1
ここで、n1 > n2 なら COSθ1 < COSθ2 なので θ1> θ2 となります。そこで θ1を小さくしていくと θ2=0 という場合が生じ、入射された光は全反射します(図1.3.3参照)。このときの入射角が θ1= θc のとき、θc を臨界角といいます。
すなわち、臨界角θc は
θc=COS-1(n2/n1)となります。
逆に n1<n2 では、全反射が得られないことが分かります。これは、スネルの法則と呼ばれるものです。光ファイバケーブルは、コアの媒質の屈折率を n1、クラッドを n2(n1>n2)にしておき全反射できる入射角(θ1<θc)で光信号を入れたとき光ファイバ内を反射し伝達していきます
(図1.3.4参照)。
図1.3.4 光の伝達 Ⅰ
2 導波モード、伝搬モード、放射モード
光はファイバ内で、反射を繰り返して伝搬していきます。媒質内での光の経路は、いくつもあります。反射の多い経路と少ない経路で、進行距離が異なりますから、同じ入射光でも到達する時間が異なります。この伝搬速度の異なる光のひとつひとつを、光の導波モードといいます。導波モードのうち、コア内に伝搬する光を伝搬モードといい、コアから外部(クラッド)へ放射する光を放射モードといいます。 -
伝搬速度の異なる光が多いと、送信データの分解能が悪くなり伝送帯域が狭くなります。このための伝送目的にあわせ改善したファイバが多く考えられています。コアとクラッドの屈折率分布が、階段状になっているファイバをステップインデックスといいます(図1.3.4参照)。
これに対して、屈折率分布を放物線状にして各モードの伝搬時間を揃えるようにしたものをグレーデッドインデックスといいます(図1.3.5参照)。
図1.3.5 光の伝達Ⅱ
表1.3.1 光ファイバの種類